本書は、家族の認知症に不安を抱き始めている人のために、その解決法として、国が進める「成年後見制度」ではなく、民法から派生した特別法である信託法に根拠を置く財産管理の手法「家族信託」を使ってください――と提言するために書いた実用書です。
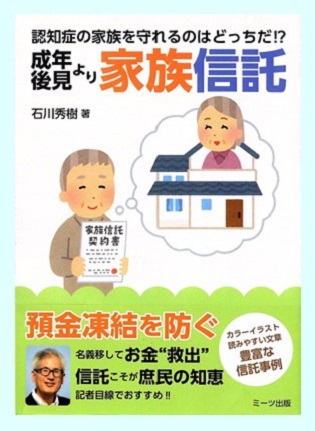
▲『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』
銀行は変わりました。高齢の方は、認知症でなくても、大金をおろしたり送金しようとすると、銀行から「待った!」をかけられるでしょう。
高齢者は銀行にとって《危険な存在》取り扱い注意の人になっています。
第一に、意思能力が問題とされ、第二には「詐欺に遭わないか」と心配され、一身に注目を注目を集めることになります。どちらの“ミス”があっても、銀行としては大問題。行員たちはナーバスになっています。
その結果、お客さまに認知症のきざしが見えると銀行は緊張し、窓口から役席、支店幹部と相談が上がっていくにつれ「問題」は過大にリスク評価され、口座の凍結に至ることになります。
本人や家族が抗議すると、「お客さまの場合は成年後見制度をご利用ください」と突き放されることに。
◎目次リンクから本書の▼中身抜粋、または▼わかりやすい解説記事をお読みいただけます
 本書は、認知症対策の公的制度である「成年後見制度」の現行運用実態には疑念があることを書いています。批判する以上、それに替わる救済ツールをしめさなければなりません。「家族信託」です。その上で、本書冒頭で「成年後見のどこが問題なのか」を指摘しました。2017年にブログに書いた下の記事が下敷きです。とても興味深い内容なので、ぜひお読みください。
本書は、認知症対策の公的制度である「成年後見制度」の現行運用実態には疑念があることを書いています。批判する以上、それに替わる救済ツールをしめさなければなりません。「家族信託」です。その上で、本書冒頭で「成年後見のどこが問題なのか」を指摘しました。2017年にブログに書いた下の記事が下敷きです。とても興味深い内容なので、ぜひお読みください。
▼▼▼ 下記記事は2016年2月にブログにアップして以来、80万人超の方々に読まれてきました。
《完全版》★使ってはいけない「成年後見」。認知症対策の切り札にならない。その災厄は家族を巻き込み、離脱できず苦悩が続く!
幻冬舎GoldOnlineにも記事抜粋を提供!
※幻冬舎GoldOnlineが、本書のコンテンツに関心を示し令和3年3月半ばから計7回、本書の中身抜粋をアップしました。「チョイ読み」よりもずっと長く本書のエッセンスをお読みになれます。
目印に、ブルーのリンクの「見出し」に❶から❼までの数字を打ちました。ご参考にしてください。
また本書の理解に役立つ「関連記事(囲み枠)」も、目次タイトルの近くに追加しました
■ □ ■
まえがき =全文抜粋▼▼▼
★超高齢人生はどしゃ降り!? お金、認知症、家族のこと――家族信託で乗り切る方法<本のまえがきを紹介>
第1部 認知症と戦う
財産凍結の時代が来た!
成年後見より家族信託を使え
※▼▼▼まずはプロローグ全文を。信託とは何かがズバリわかります。
★「老後のお金の管理、家族の私に任せて!」家族信託とは何かを超簡単に解説
第1章 なぜX氏は家族信託をしたか
※▼▼▼のリンクから、第1章「X氏」の全文をお読みいただけます。
★家族信託の基本は《夫婦を共に守る受益者連続信託》だ。超重要な「章」を家族信託の本から丸ごと抜粋 !!
資産1億円のX氏一家
家族の絆はあるのに今は“別々家族”
資産に比べ「使えるお金」が少ない
夫婦の入院・施設費に毎月30―50万円
2年8ヶ月でお金が尽きてしまう⁈
認知症で凍結されたら「家」も売れない!
「大きなお金」は動かせるお金に戻せ!
応急対策では老後資金に足りない
認知症の影響は「凍結」だけにとどまらない
凍結預貯金を動かせるのは後見人等だけ
では「成年後見」を使っていいのか
凍結解除したお金は家族に渡されない
成年後見の費用、時には1000万円を超えることも
成年後見制度を申し立てると施設を選べない
家族の思いとズレている成年後見
家族信託は、依頼者の思いに応えてくれる
家族信託なら「実家売却」もスムーズ
妻を第2受益者にしておけば安心
追い込まれての成年後見だけは避けたい
認知症に楽観は禁物、時間との勝負と心得よう
第2章 成年後見と家族信託でできる事
――家族の役に立つのはどっちだ,
まったく異なる2つの制度
信託の受託者には“凍結”解除を期待するのは筋違い
▲幻冬舎GoldOnline版よりコチラ▼▼の方が広範囲を要約しています
★成年後見VS家族信託「認知症対策」を一覧表で比較した![できること]と[できないこと]、後見の威力は限定的、意外に使える“家族の力”
成年後見人には別の問題が……
認知症高齢者の資産、2030年に215兆円

認知症になる高齢者の数が増加しています。金融機関のなかには、認知症とわかると預金者の口座を凍結してしまう銀行もあります。家族の介護費用を引き出したいのに引き出せない…なぜこのような納得がいかないことが起こるのか? そこには、銀行側の本音が隠れていました。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!?成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
「家族がうるさいから“凍結”」だなんて
金融庁は「凍結しろ」と言っていない !!
本人に意思能力があれば銀行とも戦える
不動産処分は家族信託の得意技
不動産処分、成年後見人のできることは限定的
してほしくないことまでする成年後見人
老親の株取引をやめさせたい、が通らない!?
誘っておいて、止める時には「後見人を」ですか?
証券大手の英断、受託者が運用できる証券口座を開設!
相続放棄には後見人が欠かせない
遺言より強力、家族信託の承継機能
家族信託で「生前贈与」はすすめない
会社や事業に関すること、成年後見人は判断しない
強い権限も特殊詐欺には無力
後見開始すると、家族は「身上監護権」を失う⁈
複数の専門職後見人となることさえある
家族の出番が消し飛んでしまった!
身上監護そっちのけの後見人も
「延命」の可否を決められるのは本人だけ
<コラム>『大事なこと、ノート』を提供しています
関連記事▲▲▲「私の医療へのお願書」付き、PDF版ノートを差し上げます
延命措置をするかしないか、深く考察しています。ぜひご参考に。
★『大事なこと、ノート』を刷新、PDF版に。あなたの後期医療を託す《医師へのお願い書》付き。延命について考えてほしい!

認知症になる高齢者の数が増加しています。残された家族がお金で困らないように、「成年後見制度」と「家族信託」の2つの財産管理の方法が有名ですが、両者の違いはどこにあるのでしょうか? 使い分け方を解説します。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!?成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
成年後見人は、本人を代理して単独で行為
家族信託は本人の“伴走者”
家庭裁判所がにらみを利かす成年後見
財産を受託者の名義にして、管理してもらう
委託者の生活は何も変わらない
任意後見契約もおすすめしない
Ⅲ 安全を指向し堅苦しくなった成年後見

認知症になる高齢者の数が増加しています。銀行は、認知症になった家族に「成年後見人」になって財産管理をするようにすすめるケースが多いですが、良かれと思ってかも知れぬこの行動には大きな勘違いがあります。これまで、数多くの認知症家族の問題解決にあたってきた行政書士が解説します。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!?成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
「家族後見人は減らす」に方向転換
後見人の解任は「×」、後見からの離脱も「×」
「しまった!」と思っても引き返せない制度
<参考①>家族が成年後見人になれない15の理由
関連記事▲▲▲親族間に意見の対立、流動資産が多い…等々
★家族が成年後見人になれない15の理由
<参考②>家族が成年後見人を使った方がよい場合
<緊急ニュース>成年後見は「親族が望ましい」と最高裁
関連記事▲▲▲親族後見は少しも増えていない。その理由とは……
★「15の理由」だけではなかった、家族が後見人になれない本当の理由!専門職が「あなたでは無理。私の名を候補者欄に」と誘導
第3章 「認知症」と「家族信託」
――誤解される「認知症」との戦い
Ⅰ 認知症、誰もが知っているのに知らないこと
認知症は「病名」ではありません
認知症は脳の誤作動。「痴呆」とは違う
Ⅱ 「認知症」と知られただけで“特別扱い”
Ⅲ 老後資産の凍結は13年前から深刻だった!
2006年が“預金凍結元年”
突然「わが家の認知症問題」に遭遇する
6割の人が「最後は1人になる」超ソロ社会
2人に1人は認知症問題に直面する
Ⅳ 認知症と診断されたら家族信託は無理!?
関連記事▲▲▲むしろ銀行と司法書士が“高い壁”
★家族信託の契約、「認知症と診断されても即アウト」ではない! 今すぐ決断すれば「セーフ」のケースも少なくない
「認知症」の症状は千変万化
一度判断されたら“逆転”できない
「補助」と「保佐」の境目は医師でもわからない
銀行が「認知症」を疑うとき
高齢社会に追いつかない私たちの常識
不動産の“凍結”も進行している!
司法書士は「保佐相当」でアウト!
司法書士の判断が信託時機の限界を決める
成年被後見人、被保佐人になると地位を失う
預金を崩せなければ家族信託は無理!
長谷川式テストに戸惑うとき
★代理人カードを使え! 認知症による口座凍結を当面は回避できる。あくまで暫定ツール、限界が来る前に次のステップに進め!
第2部 受益権に切り込む
家族信託が民法で出来ないことを
可能にしてしまう理由(わけ)
関連記事▼▼▼難解な受益権の前にシンプルな解説を
★家族信託とは何か/財産を先に託して“管理権限”を与え、私のためのみにお金を動かさせる財産管理手法
第4章 家族信託の本丸・受益権とは
――委託者の“分身”が活躍できる原動力
Ⅰ 受益権を徹底解説
受益権は一種の“方便”だった!
不都合な現実をなんとかするために
発想がぶっ飛んでいる信託法
強すぎる所有権を何とかせよ!
信託で所有権は「名義+受益権」となる
「委託者=受益者」という大発明
家族信託の原型は商事信託に似ている
「人を頼みにする」という発想も大事です!!
委託者の当初の意思が“凍結”される
委託者が望めば代々の承継者まで決められる
Ⅱ 実際に受益を得るとは、どういうこと?
(金銭)給付されたお金の使い方は自由
(自宅)住み続けることも受益権
(1棟の収益マンション)収益受益権と元本受益権がある
信託の終わり方までち密なシナリオを
第5章 信託の2大障壁、解消
──受託者用通帳と家族信託用証券口座が登場
Ⅰ 家族信託に見向きもしなかった業界が変化
三井住友信託銀行が先駆け !!
信託法に「通帳」についての記述はなし
「信託受託者」がわかる通帳!!
受託者のアパートローンもOK
差押えられず、受託者の相続財産にもならず
銀行は、受託者の項目に注目している
Ⅱ 銀行が受託者通帳を作ってくれない時の対処法
通帳なしの管理では不十分
決済用普通預金口座は“切り札”になる!
信託契約書に口座番号まで明記しておく
税務署にも信託したことを伝える
自信をもって「信託通帳の代替になる」と言える
Ⅲ 「株や投資信託はもうやめて!」を実現
野村証券が「家族信託口座」を開設!
一代限りの自益信託が基本
口座名は「家族信託 (受益者名)口」
他社から株や投信を移管するのは難事業!?
「75歳ルール」のときに3つの選択肢
第3部 家族信託の事例
第2受益者を置けることが
家族信託の大きな魅力に
第6章 委託者死亡で終了する家族信託
――家族信託のプロトタイプ
遺言より強力な約束としての機能も
ふだん着の契約書にしたい
Ⅰ 「いざとなったら居宅売却」型信託
受託者のために信託の方向性を示す
金銭を追加信託することも可能
家族信託の3当事者
委託者にも受託者にも贈与税はかかりません
必ずしも委託者死亡で信託は終了しない
信託財産は分別管理しなければならない
不動産の分別管理は確立している
※コチラ▼▼▼は「居宅売却型信託」の解説記事です。
★よくわかる家族信託《認知症対策の定番》いざとなったら居宅を売る家族信託を解説――権利者の名義を受託者の名に換えるのがポイント! あげちゃうわけではないので贈与税はかかりません
信託目録があるので取引は安全に
受託者のする仕事を細かく指示
認知症対策信託では受益者代理人は不可欠
家族の間だからこそきちんと報告
年金や自動引落は信託外の通帳で管理
思いがけない形で信託が終了したら!?
委託者に財産を戻す場合もある
税制上、家族信託は「ないもの」とみなされる
家族信託の契約書は“超遺言”
あらゆる場面を想定して用意しておく
主役なのに受託者は「報酬なし」も多い
Ⅱ 老後の心配事、自益信託で解決できる

認知症になる高齢者の数が増加しています。金融機関のなかには、不正防止の観点から、認知症とわかると預金者の口座を凍結してしまう銀行もあります。今回は、残された配偶者がお金で困らないように、生前からできる財産管理の方法について解説します。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!?成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
老後ど真ん中の対策が抜けている!
家族信託は自分の死後も大切な人を守る
1人だけを信託で守れればいいの!?
80歳までは元気でも、その先はわからない
信託の財布を小分けしないでください
Ⅳ 収益アパート管理型信託
バブル期の収益不動産ブームのツケ
案に相違して妹が受託者に名乗り
信託したことで柔軟な経営判断が可能に
受益権の形で財産を承継させる
家族信託で契約凍結リスクを回避
受益権を活用して“争族”を防ぐ
受益者連続信託の落とし穴
Ⅴ 事業承継に使える自社株信託
経営者の認知症は会社を追い詰める
成年後見では会社の苦境を救えない
信託すると「議決権」は受託者に移る
後継者の力量を確認しながら自社株承継を行う
指図権を行使して後継者を育てる
逆信託で後継者を伸び伸び育成
将来の自社株高騰に対処する方策

認知症になる高齢者の数が増加しており、判断能力があるうちに「相続財産」について対策をしておくことが大切です。そこで候補として挙げられるのが「遺言」と「家族信託」。今回は、両者の違いと、相続発生時にどちらが優先されるのかについて解説します。※本連載は、石川秀樹氏の著書『認知症の家族を守れるのはどっちだ!?成年後見より家族信託』(ミーツ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
書き換えや“相続人の謀反”
成年後見人が相続財産を勝手に処分
遺言では生前対策が行えない
遺言は信託に口出しできない
第7章 委託者死亡後も続く家族信託
――○○なき後に大切な人を守る
信託のみが成し得る手法
Ⅰ 夫なき後の認知症の妻の暮らしを守る信託
Ⅱ 最良の選択を、見誤らないでください!
末期がんの夫、妻は認知症、どうしたら妻を救えるか
任意後見では認知症の妻は救えない
夫に成年後見人を付けても無意味
負担付き遺贈の遺言も難点あり!
家族信託を使えば認知症の妻を救える!
AからBに受益権が移っても管理するのは受託者
中途半端な財産にして大切な人を救う
委託者の健康状態に構わず早めに
Ⅲ 障がいをもつ子の、親なき後の信託
『この信託は長期化するぞ!』
受託者の逃げ道をつくっておく
受託者主導であえて信託に見切りをつける
信託終了時に公的後見制度に託す
「特定贈与信託」は有用だが使いにくい面も
Ⅳ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用
受益者死亡で受益権はいったん消滅!?
3番目の受益者は遺留分減殺請求ができるのか
受益権は相続により移転するのではない!
信託の期間は30年目以降の新受益者死亡まで
遺留分については、楽観的に考えない
問題は「遺留分」だけにとどまらない
第8章 家族信託の困った、諸問題
――後継受託者がいない、
委託者が分かってくれない
Ⅰ 受託者不足の家族信託をどうする?
士業の受託者を「NO」とする信託業法
誰も他人に自分の財産を管理されたくない
管理型信託会社を受託者に
ここでも法定後見を“よりどころ”とする
Ⅱ 委託者が「うん」と言ってくれない
母が入院前に通帳を託してくれた
証券口座は父とふたりで管理
通信手段を断つことまでやった
家族がコケにされてたまるか!
100万円以上の「定期」は作るな!
銀行は変わってしまった、と親に刷り込んで!
終章 家族信託契約書ができるまで
※コチラ▼▼▼は静岡県家族信託協会の例です。
★家族信託の手続きの流れ<契約書作成と報酬>
Ⅰ 家族信託のパンフレットを活用
□初めてのヒヤリング □財産構成の確認
□問題点の洗い出し □使うツールの提案
□報酬と実費を見積もり □受託者・受益者決定
□家族会議で意思統一 □信託契約書の下書き
□関係機関と折衝 □契約書案を決定
□公証役場で契約締結 □登記や通帳等を作成
□家族信託の運営
Ⅱ 専門家に相談って、誰に頼ればいいの?
命にかかわる大事を、素人には頼まない
話をよく聴いてくれる専門家を見つけよう
自分の仕事に誘導する専門家は避ける
長文メールの返信をくれる先生を選ぼう
あとがき
 家族信託は生前対策と想い通りの相続を実現させるための最強ツールであることを立証した本『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』の「目次」と「記事抜粋」は▼▼▼コチラからご覧ください。
家族信託は生前対策と想い通りの相続を実現させるための最強ツールであることを立証した本『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』の「目次」と「記事抜粋」は▼▼▼コチラからご覧ください。
★『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』2冊目家族信託の本の「目次」と「記事抜粋」です。
<最終更新:2022/11/24>
←サイトのトップページへ
この本を書いた人
家族信託に関心がおありですか? ※最新のパンフレットを差し上げます

家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻の
パンフレットを作りました。
家族信託は二刀流です。(A)
認知症対策だけではなく、(B)
思い通りの相続を実現させるツールでもあります。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。この
メールフォームか右の
QRコードからお申し込み下さい。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)

▲認知症対策の定番、ベストセラー

▲相続対策に使う家族信託の本

▲最左の本を改題(Kindle版)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
![]() 本書は、認知症対策の公的制度である「成年後見制度」の現行運用実態には疑念があることを書いています。批判する以上、それに替わる救済ツールをしめさなければなりません。「家族信託」です。その上で、本書冒頭で「成年後見のどこが問題なのか」を指摘しました。2017年にブログに書いた下の記事が下敷きです。とても興味深い内容なので、ぜひお読みください。
本書は、認知症対策の公的制度である「成年後見制度」の現行運用実態には疑念があることを書いています。批判する以上、それに替わる救済ツールをしめさなければなりません。「家族信託」です。その上で、本書冒頭で「成年後見のどこが問題なのか」を指摘しました。2017年にブログに書いた下の記事が下敷きです。とても興味深い内容なので、ぜひお読みください。![]() 家族信託は生前対策と想い通りの相続を実現させるための最強ツールであることを立証した本『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』の「目次」と「記事抜粋」は▼▼▼コチラからご覧ください。
家族信託は生前対策と想い通りの相続を実現させるための最強ツールであることを立証した本『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』の「目次」と「記事抜粋」は▼▼▼コチラからご覧ください。 家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。