★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう
親に認知症の傾向が出てきたと感じたら、親を促して定期預金を解約して普通預金口座に移した方がいい。
でも難しい。委任状は通用しない。第一、フロアに委任状など置かれていない。
あなたが代理して委任状を入手しなければならない。
気をつけて!行員は必ず委任状が必要な理由を尋ねる。
不用意な答え方をすると、ここで解約できる確率がゼロになる。
用意周到なストーリーと、事前の準備、それにあなたの度胸が必要だ。
本当に困ったら「金融庁」の名を出そう。
今回は成功例を紹介する。
介護度4の母が施設に入所。応答でき、委任状も自筆で書ける
Q
母は介護度4で施設に入所しています。
まだ私との応答はでき、自筆で文章も書けます。
しかし医師からは「認知症もあります」と言われています。
先日、施設を移ったので、新たに介護費用を自動振替するため甲信用金庫に母の口座を設定しなければなりません。
それにつき、東京の乙都市銀行にある母の定期預金を解約して、甲信用金庫の普通口座に全額を振り込んでもらうつもりです。
委任状と「定期預金払戻書」は母に自筆でなんとか書いてもらいました。
この2つを持って、東京の乙都銀と交渉するつもりですが、うまくいくでしょうか。
預金の凍結、近ごろ頻発。よい対応を引き出すには“技術”がいる
A
お母さんは認知症でも、他人とも意思疎通はできるのですね?
(複雑な会話はできないが「何かをほしい」と意思表示はできる)
最近は、高齢者、特に認知症にかかっている高齢者が「定期預金」を解約するのは非常に難しくなっています。
つい2、3年前とも、明らかに違って来ています。
「預金凍結」という言葉を聞いたことがありませんか?
かつてはよくよくのことがなければ”凍結”はないと思っていましたが、今は様変わりです。
非常に多くの人が銀行の”過剰反応”に泣かされています。
こんなことで成年後見制度に誘導されては、たまったものではありません。
(しかし実際には、毎年4万人近くがまさにこの問題で、成年後見の申立てをしています!!)
ですから、はじめに「ハードルは高い」と言っておきます。
しかし、不可能ではない、と思います。
逆にこれが不可能であれば「銀行、死ね!」の事態、と言うべきでしょう。
なぜならお母さんは、認知症ではあるが、一定の事理弁識能力はあるからです。
定期預金を解約して介護費用に回す必要性は、当人(お母さん)であれば直感的に理解できますからね。
銀行では「認知症」と言うな!先入観を与え損するだけ
委任状と定期預金払戻書は、お母さん手書きのものがあるのですね?
あなたがお母さんの地元の信用金庫でこの2つの用紙を入手したのは大正解でした!
A都銀で入手しようとしたら、行員に根掘り葉掘り理由を聞かれたでしょう。
(冒頭に書いたように、都銀のフロアに委任状は置いてないのです。
委任状で何とかなる、は昭和時代の話。今は行員との会話が必須です)
ともあれ2つの書面を入手できたのは幸運でした。
A都銀に持参するのは
①甲信用金庫にあるお母さんの通帳
②施設からの振替依頼書
③お母さんの後期健康保険証と介護保険証(本人確認のため)
念のために④お母さんの届出印(甲信金・乙銀行)と実印、印鑑証明書を持参の上、東京の乙都銀と交渉してきてください。
お母さんが認知症であることはゼッタイに言ってはいけません(銀行に先入観を与え不利になるだけです)。
「施設に入っており、車いすで来るのは難しい」と言うのです。
そしてここがポイントです、覚えておいてください。
銀行は本人の意思確認のため、自宅に電話をします。
(施設にではありません。口座開設時に届け出た「自宅」に掛けてくるのです)
一応銀行に施設に入所している事情を話せばいいですが、聞き入れないでしょう。
その場合は、日時を決めてもらい、施設に事情を話し一時帰宅するしかありません。
※用意周到にするなら、前もって一時帰宅しておく。その日に都銀と交渉。
自宅には母だけでなく、始めに電話を取る人を待機させておく。
お母さんが直接電話を取れば(前もって言ってあっても)混乱するでしょうから。
銀行が歩み寄らなければ金融庁を頼りましょう
銀行側があなたの説明と要望(日時を決めて電話)を受け入れない場合は、金融庁に電話しましょう。
金融庁は銀行名と支店、担当者まで尋ねますから、正確に事実を伝えてください。
(銀行には「困ったので金融庁に相談してみる」というのも良策です。銀行は譲歩するかもしれません)
【注】金融庁の相談窓口は以下の通り。
「金融庁・金融サービス相談室」
○電話番号での通報 :0570-016-811
○ファックスでの通報 :03-3506-6699
○ウェブサイトでの通報:https://www.fsa.go.jp/opinion/
○文書(郵便)での通報:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館金融庁 金融サービス利用者相談室
金融庁に訴えるまでもなく、銀行が何らかの対応をしてくれることを祈ります。
さて、銀行からの電話にお母さんが「はい、そうしたいです」と答えられれば、定期預金の解約を断る理由はなくなります。
また、東京に行く前に、地元の甲信金とも同じやりとりをする必要があります。
しかし、東京ほどは難しくないはずです。
施設からの「振替依頼書」を見れば事情は理解するでしょう。
そのくらいの忖度(そんたく)ができるようでなければ、地元銀行の価値がありません。
「甲信金はこの辺の事情を承知してくれており、(乙都銀からの)入金待ちですよ」
と都銀側に伝えれば、乙銀行の重い腰もあがるのではないでしょうか。
全銀協の指針が出ても銀行との交渉には作戦が必要
【乙都銀との交渉結果】
※この作戦は、金融庁に駆け込むまでもなく、うまくいきました。
受け答えした行員に「あなたのお名前は?金融庁に相談したいので教えて」と聞いた途端に行員は上席と相談し、OKとなったそうです。
本人が窓口に行かずに定期預金を解約でき、成年後見を回避できた、けうな例です。
この記事の直後に、全国銀行協会は「家族の代理引き出しについての指針」を全国の銀行に流しました。(2021年2月)
残念ながら、それで一気に「口座凍結の危機」解消になったわけではありません。
銀行はあくまで「お客さまが成年後見制度を使ってくれることがベター」と考えているからです。
ゆえに、銀行との戦い方はコチラ側が周到に作戦を練る必要があります。
全銀協に指針を出すよう促したのは金融庁です。
金融庁も「認知症➤口座凍結は大きな問題」と考えていますから、相談してみる価値はありそうです。
<初出:2019/1/28 最終更新:2024/1/24>
家族信託は全国対応しています。
あなたの家でお悩みの問題をお聴かせください。
成年後見制度に委ねるより、家族信託という手法を使う方が悩み解消につながるかもしれません。
家族信託は委託者と受託者の契約ですから、すべての事案でオーダーメイドの対策を講じることができます。
成年後見人は意思能力を失った本人の代理なので、将来へ向けての「対策」は一切できないのです。
家族信託なら財産管理から相続対策のことまで、契約の中に盛り込むことができます。
《このようにしたい》という想いがあれば、受託者に動いてもらえます。
実際にあなたはどのような問題を解決したいですか?
メールフォーム「ボタン」から相談したいことを、具体的にメールにお書きください。
石川秀樹が専門家としてご家族にとって最良の解決方法を考え、お答えします。
※異変に気づいたらすぐにご相談ください。相談は無料です。
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》
 家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)生前の対策や思い通りの相続を実現させる最強のツールです。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
家族信託サイト.jpg?fit=708%2C154&ssl=1?1714217261)





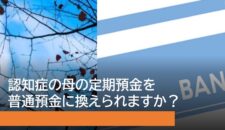




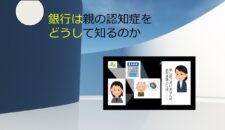







家族信託パンフレット.jpg?resize=312%2C217&ssl=1)

.jpg)