★もの盗られ妄想がある母、息せき切って銀行に相談してはダメ!手遅れに非ず。家族の結束固め対策しよう
目次
ドロボー呼ばわりされてつらい
Q.
同居している85歳の母の様子がおかしいので心配しています。
財布をよく失くし、先日はおろしてきたばかりの年金を置き忘れてしまったようです。
「あんたが盗ったの⁉」とすごい形相で迫られ、ほとほと困惑しました。
「通帳を返せ!」といわれた時には頭に来て、「いつもいつも何やってんだっ!!」と、つい怒鳴ってしまいました。。
以前の母とはまったく違うので、悲しいやら悔しいやら……。
こちらはどう対応したらいいのか。行政に相談したら何とかなるのかな……。
こんな調子でお金の出し入れができるのか、銀行と相談した方がいいのでしょうか。
息せき切って銀行に相談してはダメ!!
A.
(親の認知症の問題で今どき銀行と相談したい、なんて……。『うわぁ、今どきこういう人がいるのかぁ』と、ちょっと焦りました。それで、急いで以下のように返信)
メールを読ませていただき、太田さん(仮称)の困惑ぶりはよくわかりました。
でも息せき切って今、銀行と接触しないでください、絶対に!
相談したらアウトです。
◆症状の出方が最悪なので家族は苦労する
お母さんのご様子は、アルツハイマー病の初期症状だろうと思います。
いわゆる<もの盗られ妄想>。
元々のお母さんの性質ではなく、病気のために脳の一部が障害され猜疑心が強くなってしまうのです。
それで財布やお金などを隠すのですが、その隠し場所を忘れてしまう、あるいは隠したこと自体を覚えていない。
脳は合理的にできているので、[在るべきところに物がない=誰かが盗った]になり本人は「盗られた」と認識するのです。
しかし言われた方は、病気と分かっていても腹が立ちますよね、ドロボー呼ばわりは。ショックを受けます。
認知症の症状はさまざまですが、もの盗られ妄想は最悪な出方の一つ、最も運の悪いケースです。
本人の隠されていた性格が病気の影響で「顕在化してきた」というものではありません。
脳の部位のどこが障害されたかだけの差ですから、人によっては聖人のように気前が良くなる人もいます。
この点、自分では出方を選べませんから、運不運の問題です。
でも、キツイですよね、子の立場としては。
このように、お金にこだわる人が相手だと、家族信託をしても成年後見人を付けても、関係する人は大苦労します。
どちらの場合もやるべきことは「財産管理」ですから、本人の財産を預かることになります。
本人にしてみれば(何も盗られていなくても「盗られた、持っていかれた」と騒ぐくらいですから)不安にかられて何度でも執拗に相手を責めるでしょう。
嵐がやむのをじっと待つ心境の信託受託者や成年後見人は、心乱れると思います。
◆失せ物はとんでもない所で見つかる
お母さんへの対処法は、本人の言うことに逆らわないこと。否定しないこと!
とてもくたびれますよ。でも我慢強く、お母さんと一緒に探して財布や通帳を見つけてあげてください。
『何度も盗難が続く』と本人は思っているわけですから、(探す側から見ると)とんでもない所に隠すのが常で、探すのは楽ではありませんが。

おだやかにボケてくれればいいのですが……
見つけたとき、「お母さんが自分で隠したんだよ!そんなお金、盗りはしないから隠すのはやめろよ‼」と叱り飛ばさないでください。
叱っても、『この子は冷たい』『盗ったくせに私のせいにする』と悪い方向に向かうだけです。
それよりも「見つかってよかったね」と喜んだ表情を見せてください。
「お母さんが用心してしまっておいたんだね。僕らはお母さんのお金を盗んだりしないから隠さなくても大丈夫だよ」とやさしく諭す方がうまくいきます。
◆いずれ銀行とトラブルを起こす恐れがある
”盗難騒ぎ”とはいえ、今は家庭内の話で終わっていますからいいようなものですが。
お母さんがお金を自分で管理する限り、いずれ銀行と必ずトラブルを引き起こします。
「通帳を失くした」「カードが見つからない」「暗証番号を忘れた」「いつの間にか金額が減っている」
「預金の引き出しを頼んだのに、お金をもらってない」
などといった相談や苦情……。
原因は自分。記憶障害でつい昨日のことを覚えていないので、勝手なストーリーを脳が作り出した結果です。
でもお母さんは、そのようなことは露ほども考えずに自分を<被害者>と思い込み銀行を責めるようになります。

高齢者にとって銀行は、大きなカベになります
◆銀行は成年後見制度の利用を促す
こういうことを銀行にやってしまうと、最悪の場合、口座を止められ預金を下ろせなくなってしまいます。
預金者が認知症により判断能力を失った、と判断すれば銀行は、自らを守るために預金口座を凍結してお金の動きを封じます。
せっかく定期預金に数百万円あっても解約できなくなり、「お金はあるのに、お金で困る」ことになってしまいます。
これを解消しようと家族が乗り出しても、ヤブ蛇になります。
銀行はお母さんには「判断能力がない」と見ていますから、お母さんからの委任も代理も成立していないと考え、家族が交渉しても口座の凍結解除には応じません。
銀行が言うのは「後見人を付けてください」だけです。
その言葉をうのみにして成年後見の申立てをしたりすると、以下のようなことになります。
長期戦を覚悟して「家族の結束」を図ろう
認知症やアルツハイマー病が引き起こす問題の解決は、短兵急にやろうとしても無理です。
(銀行での預金口座凍結さえ防げばそれで解決、にはなりません。これは肝に銘じてください)
あなたが真っ先にすべきなのは、❶長期戦を覚悟すること。
そして、あなただけが抱え込まず兄弟姉妹がいるなら❷兄弟姉妹を招集して《母親の現実》を家族全員で共有することです
今後どうするかの戦略を練るのは、家族全員が「今後の道のりは困難を極める」ことを承知してからです。
◆症状悪化を防ぐため専門医に診てもらう
そこが固まったら、お母さんを認知症の専門医(精神科、脳神経内科、脳神経外科、老年科など)に診てもらいましょう。
医師に先入観を与えないよう、自分の憶測を交えずに、見たままのお母さんの行動を伝えましょう。
(素人のこちらが「認知症でほとほと困っている」などと決していわないこと。判断するのはお医者さんです)
認知症は今のところ治す薬はありませんが、進行を遅らせる薬はいくつかあります。
病院に連れて行くのは「もろ刃の剣」という面もあります。
家族信託にしても任意後見にしても<契約>ですから当然、本人の意思能力・判断力が必要です。
その能力が認知症などにより失われた、あるいは著しく減退している場合は契約できませんから、「可能性」を縛ることになります。
しかし今回は(そんなことを考えるより)事態は切迫しています。
これ以上悪化させない、ということを最優先に考えなければなりません。
専門医なら「妄想」や「怒り」を抑え、緩和させる薬を処方できますから、まずは“暴走”を止めましょう。
◆症状が落ち着いたら代理人カードを作る
症状が落ち着けばお母さんは、(運がよければ)軽度認知障害=MCI:Mild Cognitive Impairmentの状態にとどまり、契約能力が残存しているかもしれません。
もの盗られ妄想が緩和され人との会話が普通にできるまでに戻ったら、今度はお母さんと2人で銀行(郵便局)に行き、普通預貯金口座の代理人カード※(家族カード)を作ってもらいましょう。
代理人カードは、「本人(通帳の名義人)と生計を同じくしている家族=つまり同居家族ですね」なら作ってもらえます。
さらにゆうちょ銀行の口座なら、家族に限らず名義人本人が希望すればカード保持者の制限はありません。
※コチラの記事を参考に↓↓↓
それと同時に「定期預金」にしているお金を、代理人カードで出し入れできる普通預金口座に移し換えてください。
さらに公共料金や固定資産税、クレジットカードの引落などをこの口座に設定し直しておけば、当面は乗り切れるかと思います。
※定期預金の解約は簡単ではありません。コチラの記事を参考にしてください。
行政に相談すれば成年後見を勧められる
緊急避難的な応急の策を紹介しました。
太田さんは質問の中で「行政に相談したら何とかなるのかな……」とつぶやいていました。
気になったので説明しておきます。
自治体によって大きな差があるので「全部だめ」とはいいませんが、行政は、きめ細かで各家庭で使える《認知症対策》など持ち合わせていません。
大概の自治体は「地域包括支援センター」を軸として、成年後見制度を使ってもらうというのが基本、と考えているようです。

行政に認知症の母親のことを相談しても頼みにはならないかも
でもこれは、私から見ると<行政組織の限界だなあ>としか思えません。
各組織・機関で一所懸命に任務を果たしている人たちには申し訳ないですが、今の成年後見制度には限界や『暗部』もあります。
少なくとも「認知症」と聞いたら条件反射のように「成年後見制度」一択と思い込むほど素晴らしい制度ではありません。
普通の市民にとって、お金の管理を一生涯他人に任せる(あるいは他人の監視下に置かれる制度)には、強い抵抗感があります。
この庶民感覚がないまま、「国が勧めている制度だから」と、他の選択肢を知らないで成年後見制度に誘導されては本当に困ります。
今回の太田さんのお母さんの認知症問題は、入り口が「もの盗られ妄想」から始まっていますから、行政に相談すれば(※普通の市民はそもそもどの課に行けば認知症の親の問題を聴いてもらえるのかさえわからない)地域包括支援センターを紹介されるのが普通です。
その地域包括支援センターは、認知症と聞けば「イコール成年後見制度だ」と思っています。
他の選択肢まで調べている人は少ないですから、今私が記事の前半で書いたような「当面の解決策=処方せん」を話すことはないでしょう。
ですから太田さんは、行政が言うのだからといきなり成年後見制度に飛び込むのだけはやめてください。
代理人カード、家族信託、商事信託 6つの選択肢
解凍が長くなったので、太田さんのケースで取り得る対応策を列記します。
もの盗られ妄想が小康を得て、お母さんには意思能力(契約能力)が残存している、という前提での選択肢です。
●1 通帳を当分使える状況を作るだけなら、代理人カードで何とかやっていける。
●2 凍結防止と近い将来に発生する相続までの対策をしたいなら家族信託。
●3 兄弟姉妹に考え方の違いがありまとまっていないなら家族信託系商事信託。
●4 家族内の対立がすでに顕著なら任意後見契約。
●5 対立というより、遺産獲得のためなら訴訟も辞さずというような子がいるなら法定後見。
●6 結局、何の対策もしない(運任せでやり過ごす)。
◆どれを選択しても関われば苦労必至
以上、6つの選択肢があります。
母親は妄想からは脱したとはいえ、お金に強いこだわりを持っています。
この場合、家族の善良な意思の下にどのツールを使ったとしても、財産管理をする当事者は大変な心労を抱えるでしょう。
1から5までのどのツールを使ったとしても、本人にお金へのこだわりがあり、理性によって自分の欲望を抑えられる能力が失われているなら、第三者が本人のお金を管理するこれらの対応法は“難事業”になるといわざるを得ません。
◆商事信託もありだが、お金はかかる
●1の代理人カードは、お金自体は本人名義の通帳に数字として残っていますが、カードを使って預金を引き出すのは代理人(子)です。ですから本人が疑いを抱く余地があります。
●2の家族信託では、本人のお金を受託者が管理する口座に預け入れ、口座の名義自体も受託者の名義に換えます。猜疑心の強さが残っている場合、この状況を委託者である本人が受け入れることはかなり難しいと思われます。
●3は商事信託ですから、本人は「金銭信託」という商品を購入したという感じです(自分のものと思える)。受託者は信託銀行ですから盗られる恐れはありません。子は引出代理人としてお金を届けてくれる存在となります。本人にとってはかなり快適。ただし、家族信託に比べ契約の自由度は低く、しかも家族信託に比較すると高額の出金になります。
●4任意後見契約。子の1人が任意後見人になっても、任意後見監督人の指揮下に入るので、お金の横領は起きにくい。ただし信託監督人は司法書士か弁護士ですからランニングコストが高くなります。また家庭裁判所が金銭の動きの最終決定者なので、本人の意思は通りにくく不満が貯まるかもしれません。
なお任意後見人を士業に頼めば安心感は増しますが、報酬が2人分発生するのでランニングコストはさらにかさみます。
●5法定後見は、本人の猜疑心がとてつもなく強い場合、すべてを疑ってかかられては始末に負えないので、強力な権限を持つ成年後見人にすべての財産を委ねておこう、という選択です。本人の希望はほぼ通らないので、本人は不満でしょう。しかし成年後見人は個々の家族の思惑とは独立して本人の財産を管理しますから、ある意味で公平そのもの。家族が親の財産をめぐって対立が絶えないようなら、このような選択もあり得ます。
「何もしない」で銀行にすがるのは超ヤバイ
●6は「何もしない」。お話にならないくらい無能な選択肢だ、と思いましたか?
さに非ずです。現在の日本では、親の認知症に遭遇してしまった家族の圧倒的な多数が(「選択する」という積極的な意思がないまま)、親の認知症問題について実際上は何もしていません。今まではそれでも通ってきたのです。銀行は今ほど認知症にナーバスではなかったからです。
もうひとつ。資産凍結に堪え得る資産家家族なら、本人以外の誰かが立替えれば済みますから。
ただし、本人が契約の当事者であるような重要事案を抱えている場合は、いずれ成年後見制度を頼ることになります。
本人の資産は“事実上の凍結状態”になりますが、それゆえにこそ手つかずに残ります。
遺産は本人が亡くなれば、遺産のすべて瞬時にして相続人が共有することになりますから(これが民法の規定)、相続人全員で遺産分割協議を行い分け合うことになります。
◆不用意な無策は成年後見必至
しかし実際は、そのような覚悟や戦略があって<無為無策>を貫くわけではないですよね。
不用意ゆえの無策であることが大半ではないでしょうか。
その場合、本人の資産が使えず家族も支えきれなくなると、やむなく成年後見ということになります。
これが「最悪の事態」かどうかは家族の関係性次第です。
本人はお金が自由になりませんから間違いなく不満ですが、お金は後見人が保守的に管理しますから家族が関与するより残ります。
すいません、皮肉な書き方をしてしまいました。
ブルーの線を引いた部分をよく考えてください。
成年後見人がお金を管理すれば、その期間、本人にとっても家族にとってもお金は不自由になります。
それは言い換えれば、誰にも中立的に効率的に管理されるということ。
親思いの子が見れば「父が不自由になってかわいそう」な状態。
一方、親の遺産に関心がある子は「そっくり残ってしめしめ」なのかもしれません。
親に法定後見を行うということは、こういう状態を作り出すということです!
◆成年後見申立て理由の92%は「凍結された預金の解除」
でもほとんどの人は、「凍結された預金の解除」(91.8%、令和4年最高裁統計)を求めて法定後見の申立をしています。
単純に、「親のために親の預金を使えるようになる」ということではないんです。
本人の資産は、本人も、家族も、アンタッチャブル[使えない状態になる]ということ。
それは本人が亡くなるまで続きます。その間、誰の思いも封印されるということ。
最高裁統計のマジック-e1697338789950.jpg?resize=600%2C461&ssl=1)
令和4年の成年後見申立て理由。預貯金の解約が90%を超えている!
子は《おやが認知症になったばかりに、こういう状態になってしまった》ということをよく考えてください。
対立のある家族にとっては、否応なく寒々と中立、これは好都合かもしれません。
親思いの子にとっては、何もできない自分を申し訳なく思うことでしょう。
このように「成年後見制度に頼る」ということは、本人にも家族にも、ドラスチックで決定的な強い拘束状態を作り出します。
「何もしない」は、経済的な余力があり家族対立のない家族なら、結果オーライになるかもしれません。
しかし、鈍感で何も気づかずに「何もできずに」成年後見に追い込まれる場合は、苦い結果を覚悟してください。
それが嫌なら、本人に契約能力が残っているうちに、つまり『母が認知症?』と思ったらすぐに●1~4までの策を講じるべきです。
◆まとめ
太田さんの場合は、間に合うかどうかギリギリの常況です。
でも焦らず、まず家族会議を開いて覚悟を決め、わが家ではどの対策を選択するかをよく話し合い、お母さんを専門医に連れて行ってください。
小康を得て、意思能力が残存しているなら家族と共に銀行に行き、代理人カードを作りましょう。
それ以上に本格的な対策が必要なら●2~4までの対策を、お母さんと家族全員で話し合って決めてください。
回答: 行政書士/ジャーナリスト 石川秀樹(静岡県家族信託協会)
(初出:2023/10/15 最終更新:2024/2/24)
家族信託は全国対応しています。
あなたの家でお悩みの問題をお聴かせください。
成年後見制度に委ねるより、家族信託という手法を使う方が悩み解消につながるかもしれません。
家族信託は委託者と受託者の契約ですから、すべての事案でオーダーメイドの対策を講じることができます。
成年後見人は意思能力を失った本人の代理なので、将来へ向けての「対策」は一切できないのです。
家族信託なら財産管理から相続対策のことまで、契約の中に盛り込むことができます。
《このようにしたい》という想いがあれば、受託者に動いてもらえます。
実際にあなたはどのような問題を解決したいですか?
メールフォーム「ボタン」から相談したいことを、具体的にメールにお書きください。
石川秀樹が専門家としてご家族にとって最良の解決方法を考え、お答えします。
※異変に気づいたらすぐにご相談ください。相談は無料です。
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》
 家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)生前の対策や思い通りの相続を実現させる最強のツールです。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
家族信託サイト.jpg?fit=708%2C154&ssl=1?1714212554)


定期預金を解約.jpg?ssl=1)




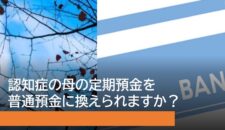






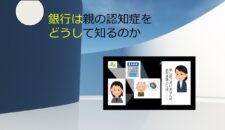





家族信託パンフレット.jpg?resize=312%2C217&ssl=1)

.jpg)