★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく遺言 <文例1>
<遺言(いごん・ゆいごん)>という言葉、どなたでもご存知かと思います。
のんびりした日本でも、最近は10人に1人は遺言を書いているようですね。
そのうちの7、8割が遺言公正証書、残りが自筆遺言ですから“自分で書く遺言”は意外に少ない。
自筆遺言が不人気というより、やはり書き方が普通の人には難しいのでしょう。
(遺言は法律効果のある文書ですからね、何と言っても)
とは言え、私はこれから「自筆遺言のすすめ」を書こうと思っています。
公正証書に歯向かうつもりではないですよ。
緊急かつ、どうしても遺言が必要な場合があるから「自筆遺言」、捨てがたいんですよ!
「遺言の効果」を知っているか知らないかで、天地の違いが生じるケースがあるんです。
たった数行の自筆遺言で、特定の相続人の窮地を救える。
むずかしい理屈は不要!時にはたった1行でOK!(「らくらく遺言」といっておきましょう)
目次
■子がいない夫婦、妻にのこすべき遺言
「らくらく遺言(いごん)」文例の第1番に紹介すべきは、永年苦労を分かち合ってきた配偶者への遺言書です。
遺言書
遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる。
平成○○年○○月○○日
静岡県静岡市○○区○○町○丁目○番○号
遺言者 静岡太郎 ㊞
民法では「配偶者」は常に法定相続人です。
言ってみれば”別格”の扱い。
配偶者以外の相続人には順位が決まっています。
第1順位: 死亡した人の子ども
※その子どもがすでに死亡している場合は、その子どもの直系卑属、つまり子や孫が相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
第2順位: 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
※父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹
※その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
■必ずしも配偶者がすべてを相続できない
このように順位が決められている中で、”指定席”を持っている「配偶者」は必ず相続できるわけですから遺言書を書く必要はないようにも思えます。
しかし別格の相続人である「配偶者」といえども、遺産のすべてが相続できるわけではありません。
法定相続人には、その”取り分”(法定相続分)が以下のように決まっているからです。
- 第1順位の子の場合、法定相続分は「 配偶者1/2 : 子1/2 」
- 第2順位の死亡した人の親の場合は「 配偶者2/3 : 親1/3 」
- 第3順位の死亡した人の兄弟姉妹は「 配偶者3/4 : 兄弟姉妹1/4 」
相続で第2順位、第3順位の相続人が登場するのは、被相続人に子どもがいない場合です。
逆に言うと、ご夫婦に子どもがいない場合は、夫(妻)が亡くなったときに妻(夫)が遺産のすべてを相続できるとは限らないということです。
※配偶者が何もしなくても全遺産を相続できるのは、第2順位、第3順位の相続人がすべていないか、全員が相続放棄をした場合だけです。
例えばこんな場合──
■亡き人の兄弟姉妹が妻を泣かせる大誤算!
<「私」には子どもがいない。両親はすでに他界、兄と妹は健在だ>
「私」が死ねば遺産はすべて妻が相続すると思い遺言も書かずにいたが・・・・。
葬儀が終わり四十九日も済んで妻がようやく心の落ち着きを取り戻したころ、思いがけなく私の妹が訪ねてきた。
「ところで義姉(おねえ)さん、遺産分割協議はいつやるの?」
妻は顔色を変えた。夫の財産は自分が継ぐものとばかり思っていたからだ。
第3順位の兄と妹。私も生前、気にも留めていなかった。やむなく数日後、妻と妹と兄で遺産分割協議を行った。
すると妹は待っていましたとばかり「わたしにもお兄ちゃんの遺産を相続する権利があるのよね」と言い出した。
兄までが同調してしまったのには心底驚いた。
おかげで私の遺産は、財産形成になんの寄与もしなかった兄妹に1/8ずつ(ふたり合わせて1/4)分けなければならなくなった。
まことに不本意な結果で、妻には深く深くおわびするしかない。
予想外の展開に妻はぼう然。彼女は、私の遺族年金で暮らしていくつもりで、いざとなれば家と土地を売って施設に入る予定であり、私ともそのように話し合っていた。
そんな妻にとって兄妹の相続分を現金で支払うことはとうてい無理な話。結局、親戚のとりなしで妻の単独所有になるはずだった私名義のわが家と土地は、妻3/4、兄1/8、妹1/8の持ち分で共有することになった。
■現金で払えず自宅が親戚と共有に
「持ち分を譲ってもそのまま住み続けられる。大した問題ではない」
とお思いだろうか? とんでもない。妻にとっては死活問題である。
不動産が共有になったおかげで兄と妹の賛成がなければ売ることもできなくなった。
説得して売ることができたとしても、売買代金の1/4もの現金を(妻から見れば何の関係もない)兄妹に”持っていかれる”ことになる。
私が無頓着だったために妻にこんな苦労をかけることになるとは。
悔しい、まことにくやしい !!
せめて(第2順位である)両親のどちらかが生きていてくれたら、妻のために快く相続放棄※してくれただろうに・・・・。
と、草葉の陰でほぞをかんでもなんの足しにもならない。
「私」はいまだに成仏できないでいる。
※ 実はこのケース、両親共が「相続放棄」の手続きをしてはまずい。第2順位の相続人が相続放棄すると権利は第3順位の相続人に移転してしまうからだ。
何の手続きもせず、妻の相続を見ているだけにするのが、息子に永年連れそってくれたお嫁さんへの“感謝”になる。
■遺言の1行で妻の苦境を避けられたのに
子どもがいない夫婦には、常にこのようなリスクがある。
「配偶者」の立場からすれば「いかにも法律の不備」と言いたくなる事例だが、そうとばかりも言えない。
財産は自ら一代で築き上げる場合もあるが、その親から受け継いだ財産がある場合も少なくないからだ。
夫婦はもともと他人同士。
夫の兄や妹は「赤の他人のお嫁さんに○○家の財産をすべて持っていかれるなんて」と感じるかもしれない。
まあ、これは見方や立場によること。
要は亡くなる人(被相続人)の考え方次第、というか「知識」に追う所も大きいでしょう。
血縁を重んじるなら『少しは兄や妹にあげたい』と思う人がいるかもしれない(たぶん少数派)。
妻の生活や感謝を考える人なら、『子がいないなら、すべてを妻に』と思う人が多いのでは?
今回の問題は、どちらの意思をもっていたにしろ、「夫」が何の手も打たなかったということ。
<問題がある>ことに気づいてさえいなかった、ということが一番の問題!
冒頭でご覧になったように、「配偶者に全財産を相続させる」にはただ1行書けばいいのです。
- 全文を自分で書く
- 日付を書く
- 署名する
- ハンコを打つ
自筆遺言書の必要十分条件はたった4つです。
■自筆遺言書の効果は公正証書と同等
時間の余裕があり、正確・確実のためならお金がかかっても構わないというのであれば「公正証書による遺言書」もおすすめできます。
しかし死期が迫っているような特段の事情がある場合、あるいは時間的な猶予がまだある場合でも、ふと配偶者のことが心配になり『どうしようか』と思ったなら、その瞬間に迷わず紙に書き(消えない筆記具を使って)今日の日付を入れて署名をし、ハンコを打ってほしい。
それですべてが変わります。
ハンコは実印が望ましいですが認印(みとめいん)でも構いません。
実印を探して(あるいは実印を作るために)後回しにするくらいなら、とにかくあなたが普段使っているハンコを押して遺言書を完成させて。
あなたが急な発作に襲われた時でも自筆の遺言書なら、手近にある布に書いても、チラシの裏や新聞紙の余白に書いても、本文と日付と署名、ハンコがはっきりしていれば有効になります(あなたが死亡した場合、相続人など利害関係のある人が家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしてもらうことになります)。
■「思い立ったが吉日」ためらわず書くべき
このように自筆の遺言書は「思い立ったが吉日」です。
文面にあれこれ迷って書かないでいるより、どうしても書いておかなければならない事項は、ふと浮かんだ瞬間に書き留めておいてください。
遺言書は完ぺきな”完成品”でなくてもいいのです。
「10」遺言したいことがあり、「2」か「3」しか書き方が分からない場合でも、それを書き留めて「遺言書」にしておくべきです。
なぜなら人間というものは、一度やりかけると「完成させないまま放っておくことができにくい動物」だから。
遺言書を一部でも書けば、非常に重要な法律文書ですから、完成させずにはいられなくなります。
一番重要なことから書いてください。
日付、署名、ハンコを押して有効なものにしておくこと。
その場合、あなたに万一のことがあっても「書いたこと」は有効に機能します。
思い立った日に書いたおかげで、あなたの希望が実現していくのです。
とにかく最も気にかかる重要なことから先に書き、遺言書の書式にしてしまいましょう。
あとはじっくり考えてけっこう。加筆・訂正、書き直しはいつでもできます。
何度でも書き直せます。(その場合、前の遺言書は必ず破棄すること。何通も見つかると混乱の元になる。遺言書は日付の新しいものが有効になりますが、前の遺言書が直ちに無効になるわけではありません。後の遺言書で訂正した部分が無効になるのであって、他の部分はなお有効です。こんなものが何通も存在すると必ず混乱します。だから最新の遺言書を書いたときは、それ以前の遺言書は完全に破棄したほうがよろしい)
■不安なら一度は法律の専門家に相談を
やや蛇足ながら。
法律の専門家の多くは、「自筆の証書遺言は(書式等に)誤りがあって無効になりやすい。字が判別できないこともある。素人がわけのわからないことを書いて、かえって相続を混乱させることがある」などと厳しい評価をしがちです。
一部うなずけるところはあります。
しかし「完ぺきな遺言」をめざして書かないでいるうちにあなたに万一のことがあったら・・・・。
今回の「夫」のように、草葉のかげでほぞをかむようでは遅い!
書けるときに自筆で書いておきましょう。これは鉄則!!
書いたうえで、落ち着いたら必ず法律の専門家にご相談ください。
不慣れな人の遺言(もちろん大半の人が不慣れです)は不備な場合も少なくありません。
しかし書かないよりずっとまし。自分がどうしたかったかが、これで分かります。
安心したところで専門家に見てもらうと安心できます。
今は法務局で「自筆証書遺言書を保管してくれる制度」がありますから、二重に安心。
書いた本人が届けなければなりません。だから、早いうちに・・・・。
<遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる。>
突然、夫の兄弟姉妹がやって来るような不測の事態を封じる”魔法の1行”を紹介しました。
相続には落とし穴がまだまだたくさんあります。
知識は絶対に必要ですから、これから順次書いていきます。
<初出:2015/11/19 最終更新:2024/4/30>
静岡県家族信託協会
静岡県遺言普及協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)
全国どこからでもお答えしていきます。
あなたの家でお悩み・お困りの問題をお聴かせください。
遺言だけにこだわりません。人生晩年のことや相続については悩みがあって当たり前。
解決法は、遺言や家族信託はもちろんですが、時には成年後見制度も必要ですし、
ケアマネさんや社会福祉協議会との連携で悩み解消につながる場合もあります。
まずは質問・ご相談ください。専門家として真剣にお答えします。
実際にあなたはどのような問題を抱えていらっしゃいますか?
メールフォーム「ボタン」から相談したいことを、具体的にお書きください。
石川秀樹がご家族にとって最良の解決方法を考え、お答えします。
※考えあぐねたらすぐにご相談ください。相談は無料です。
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》
 家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)生前の対策や思い通りの相続を実現させる最強のツールです。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
家族信託サイト.jpg?fit=708%2C154&ssl=1?1716277919)





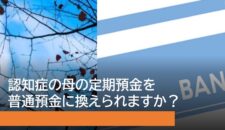

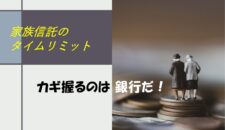







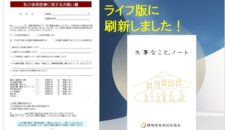

鎌倉新書.jpg?resize=518%2C221&ssl=1)

家族信託パンフレット.jpg?resize=312%2C217&ssl=1)
.jpg)
