★「延命のための延命は拒否」でいいですか!? 最期の医療めぐるおかしな”空気”
「延命治療拒否」が最近、流行にでもなっているのだろうか?
拒否するのは勝手だが、これが”社会的な空気”のようになるなら「それは違うぜ!」と言っておきたい。
目次
■100歳老人の「延命」否定発言に強い抵抗感を覚える
突然こんなことを書くのは2016年4月30日の朝日新聞朝刊に気になる記事が載っていたからだ。
「フォーラム」面の特集記事、畑川剛毅記者による<「最期の医療」正解ない問い>という記事。
「最期の医療」を取材した畑川記者の総括的な感想文だ。
全文を掲出するので、できればお読みいただきたい────

どうかと思う朝日新聞の論調(2016年4月30日、朝刊「フォーラム」面より)
100歳老人が「延命措置」について(編集者の表現を借りれば)「大胆な提言」をしている。
「75歳以上は、透析や胃ろうなどの延命措置は原則として施さず、希望する場合は全額自己負担とすべきだ」
馬詰(真一郎)さんは銀行員、企業の経理担当者として85歳まで働き、以来、奈良にホスピスを設立する運動に携わっています。心臓弁膜症を患い、要支援2。・・・・一方で「腎機能がいくら低下しても人工透析を受ける気はない」ときっぱり。───2016年4月30日、朝日朝刊「フォーラム」面より抜粋
朝刊を読んでいた家内がこの記事に気づいて読み聞かせてくれたとき、私は気にも留めずに聞き置いた。
ありがちな意見で、100歳老人の意見としての注目度はあるものの、「延命を拒否する」旨の意見としてはそれほど目新しくもない。
私自身、自分のことなら”延命拒否”するつもりで、そのような言辞を弄してきた。
■脳梗塞で鼻からチューブのはずの父が、口から食べている!
それが数時間にして、悔悛した!
悔い改めたのである。
父が入院するリハビリテーション病院でのこと。
その日、珍しく夕方遅く訪ねた。
ちょうど夕食時。
父が口から嚥下(えんげ)する様子の一部始終を見届けた!!
想像もしていなかった光景だった。
父は今年正月3日、脳梗塞で倒れた。
1回の発症で存外手ひどくやられてしまったようで、右手足がマヒ、口内も右の筋肉は硬くなり嚥下障害も出てきていた。
発病5日目にして病室で医師からは「鼻からチューブを通しますか?」と経鼻胃管栄養法を打診され、私は衝撃を受けた。
『母に続いておやじまでもが鼻からチューブか!?』
父は今、点滴している。回復を待って食事の訓練、という風に進むと思っていたのに、医師のニュアンスは
《点滴をやめてチューブに換えると長く(寝たきりのまま)生きますよ。それでもチューブしますか?》と伝えているように聞こえた。
ベッドに寝ている父の方に振り向くと、いきなり目が合った。
強烈な目力だった。
言葉はいまだ発せられないのに、《おい、断るな! 俺はチューブやるぞ》と伝えていた。
私は医師に「あんた、命の問題を立ち話かね」と返し、経管栄養への移行を指示した。
父はその病院に24日間入院。その後リハビリ病院に移った。
その24日後、口から食べる練習を始めた矢先の2月20日、自分の唾液を誤嚥して肺炎を起こし元の病院に緊急搬送された。
命が危ぶまれたが幸い、回復。
(実はその時も医師からは「(延命)続けますか?」と問われ、継続を伝えた)
さらに24日後の3月15日、父はリハビリ病院に戻った。
”鬼門”ともいうべき24日周期を今度は無事に過ぎ、イヤな予感もすっかり忘れていた5月1日、いつもの時間より遅れて見舞った私は、父の貪欲な食べっぷりを目の当たりにしたわけだった。
主食はおかゆのようなご飯に味付け、その他の惣菜もプリン様のものかトロ味を付けてあるが、お茶を除けば5皿分を完食。
「お茶は苦い」と好き嫌いを言うほどに、”食べること”がなじんでいた。
もちろん右手は使えない。左手の動きも幼児のように心もとない。
それでもおサジの柄を太いゴムで巻き、サジの先端を手前に曲げて口に入りやすいよう工夫してあるので、自らの手で(ゆっくりゆっくり)食べていた。
『とても全部は食べられまい』と思われた量を、30分もかけずに平らげてしまった。
■「75歳以上」になったら命を値切るんですか!?
父の様子はとてもではないが「75歳以上になったから」と命を値切られるようなやわな生命力ではなかった。
発症3週間後の1月24日、病床で父は90歳の大台を迎えている。
以上書いたように、2度の危機があった。
私は《ひとたび経管栄養にすれば、2度と口からは食べられないだろう》と思っていた。
だからこそ医師に「どうします?」と不意を突かれたとき、一瞬たじろぎ父の方を振り向いたのだった。
援けられたのは私だ。
父は一瞬のちょうちょもなく、明確に《俺は生きるぞ!》と伝えたのだ。
苦い思いがあるのである。母のことだ。
母は経管栄養になってすでに3年以上経過している。
パーキンソン病の進行で嚥下が難しくなり、ある日見舞うと、鼻からチューブを通されていた。
この老人病院に入院するとき私は「延命のための経管栄養はいらない」と言っておいたので、母への措置は「おやおやっ!?」といったものだったが、これまで介助されながらも口で食べている姿を見続けてきただけに、「点滴にしてくれればよかったのに」と言う気にはなれなかった。
やがて母は家族を認識できなくなった。
40年間も同居してきた家内の声はさすがに聴き分けていたが、この1年半はそれも分からない。
このような母がいながら父までが経管栄養になったので、心が少々乱れた。
が、医師が私に「どうしますか?」と尋ねたとき、父の目力はなお強かった。
だから私は医師に、何をいうか!との思いで「父には意識があるんだがね」と切り返したのだ。
丸1日医師に返答しないでいたら、翌日見舞ったとき父はベッドから渾身のまなざしで私を見、何事か告げようとしているのがわかった(言葉は発しなかったが、気配が感じられた)。
「どうする、(鼻からチューブを)やってもらうか?」と聞くと、父は大きくうなずいた。
繰り返すが父は90歳になったばかり、本人も回復の自信はなかったはずだ。
命を惜しんだとも言える。
《長くなるぞ。自分で自分がもどかしくなるぞ。これからの日々、快適ではないぞ》と言ってやりたい気が、私には少しだけあった。
もちろん父にそんなこと、言いはしない。
ただ自分のために心に問うただけだ。(ああ私は、なんとも料簡が狭い!)
しかし父のどん欲な食欲を見たこの日、『やられたな』と思った。
父よ、やはりあなたはすごい。この状況であきらめていない・・・・・。
■命のことに粗雑なエンディングノート!
100歳老人の発言にどんな抵抗感を感じたのか、お分かりいただけただろうか。
巷ではエンディングノートばやりである。
これにも私は前々から、苦いものを感じている。
私は基本的に、生死に潔い人間をたっとび、自分もそうありたいと願っている。
「延命のみを求めること」はみっともないとさえ思う。
しかし、こういうエンディングノートを見かけるとカチンと来るのだ。
粗雑すぎないか!? 「いのち」のことに対して!

「延命拒否」をすすめるコクヨのエンディングノート
これは割と売れているコクヨのエンディングノートの一部だ。
薄緑色のスクリーンを掛けたところの文章を読んでいただきたい。
延命処置(気管切開、人工呼吸器、心臓マッサージなど)を回復の見込みがない人に行うことについては、苦しい状態を引き延ばすだけという考え方もあります。
延命処置は、一度始めてしまうと途中でやめることが難しいため、もしもの時に家族の負担が軽くなるように、よく考え、意思を伝えておきましょう。
コクヨノートの編集者の、率直で迷いのない物言いに驚嘆する。
この人は、自分は歳を取らず、病気にかからず、いつも元気に生きていけると固く信じているのだろう。
こういう無邪気で容赦ない”私は正しい”感にあふれた雑な文章を読むと、ついムカムカしてひとこと言いたくなる。
■嚥下障害1つで「命を消せ!」ですか!?
「延命」を論ずべき場面は最低でも4つある。
- 脳卒中や事故、重病で意識が鮮明でないような急性期
- 治療をしてきたが回復せず、ついに死期を迎える終末期
- 老化や病の進行、病の性質により通常の食が摂れなくなった慢性期
- 認知症の進行や老化で意思疎通が難しくなった老耄(ろうもう)期
コクヨのノートが想定した場面は「1.急性期」のみ。
「3.」や「4.」が父の状況にあてはまるだろうか。
母の状況はもっと複雑だ。「2.3.4.」の混合状態ではあるが、「終末期」はいまだ訪れる気配がない。
私も母の状況は困難だと思う。
「生きている価値」がある生なのかどうか・・・・・。
しかし「鼻からチューブをやめて、点滴に換えてくださいよ」とは言えない。
(※チューブを点滴に換えても、人はすぐに絶命しないが、死期は早まる。)
私だって、母の療養をどうすればいいのか、悩んでいる。
いまだ《価値ある命なら》という思いもあるが、では今の母は価値のない命なのか?
そんな判断が誰にできると言うのだろう。
命の大事だ。私は両親の命について、医師から「どうしますか?」と何度も判断を迫られている。
『決められるなら自分で決めて見ろ!医師の責任においてお前が決めろっ!!』と言いたくなるのを、いつも抑えているのだ。
そんな命の大事を、コクヨのノートは「✔」ひとつで済まそうとしている。
こんな粗雑なノートが横行したら、大切な命が「嚥下障害」1つでいくつも吹き消されてしまう!!
■「延命のための延命」をやめさせる空気?
延命拒否論者の多くが言うように(100歳老人の論もその典型だ!)年間死亡者170万人時代(あと10年後にはそうなるそうだ)に
「これまでと同じように延命措置を施していれば医療費はいくらあっても足りない。国民全体の経済、医療を考えれば、延命のための延命はやめるべきだ」
と言われれば、「まったくその通りでございますね」とうなずきたくなってしまう。
が、分かってもらいたい。
「延命のための延命」と誰が決めるんですか!?
誰も決められないから100歳の馬詰さんは「75歳が区切りだ」と言っている。
この御仁のあまりに容赦のない、切れ味と乱暴さに、朝日新聞の畑川記者は
「延命の一律制限」という、人生の若輩者にはとても言い出せない思い切った提案に驚くばかりです。
と、まことに歯切れの悪い感想を述べるだけ。
自分の結論を言い出さずに、何が「フォーラム」か。意気地がない!!
後は読者の皆さんが考えてください。本当に「最期の医療」って難しいですね。医療費がかさむのは確かだし、「延命」の基準を設けるのはもっと難しい。
ですから読者の皆さんが考えて「延命のための延命」だけはしないように、そういう空気だけはつくっていきましょうよ───とでも言いたいのだろう。
「人生の若輩者にはとても言い出せない」から、「思い切った提案」を100歳老人に代弁してもらったように見える。
天下の「朝日」ブランドが、「延命拒否」のムードを世間に広めたいなら、もっと社会経験を積んでからものを言いなさい!
■体験を積み重ねて「解」を出すしかない
朝日の編集者がつけた見出しのように「最期の医療」に対する問いには「正解」がない。
ないからどうするのかと言えば、記者も、100歳老人も、66歳の私も、医療従事者も、さまざまな病気で生死のはざまにいる人も、その患者家族も──、自分の体験をもとにそれぞれのベストではないかもしれない「解」を導き出して、<これでよかったのか?><別の道もあったのではないか?>と悩み、苦しみながら”思い”を積み重ねていくしかないのではないか。
今の一見、「延命のための延命」が医療現場にあふれて見えるような状況も、実はここ10年来、現場で語りつくされ、やり尽くしたことの”一応”の結論であろう。
しかしその現場も、最近また流れが変わり始めている。
確かに医療費節減の圧力はあるのだろう。
一方患者や家族の側も、医療任せにしているとQOL(クオリティオブライフ、生きている質)を得られるどころか、”死ぬに死ねない悲惨”が待っているかもしれない、と、被害者ででもあるかのように恐れを感じ始めているのだ。
そんな”空気”もあって、命を預かる医療現場もかつてほど「延命措置するのが当然」とは思わなくなっているようだ。
最期の医療をめぐる価値観は、今後大いに変化していくだろう。
■筋書き通りいかなくても文句は言わない覚悟
こういうときに「揺るぎない自分の死生観を持とう」などというごう慢は、とうてい私には言い出せない。
死期を悟って(すべての医療行為を辞退して)静かに死んでいくというのが理想なれど、そんなに具合よく事態が進行するとも思えない。
病いにかかれば気力が落ちる。意思能力が失われれば、今後の措置は医師任せ、家族任せ。
だから自分の意思は今から近親者に明確に言っておかなければならない。
私は意志薄弱だから「尊厳死宣言」などしない。
(強い延命拒否の意思も、その場になればコロっと変わるかもしれないから)
願うことはただひとつ。
私に明確な意思能力が残っており、書くこと、発信能力がある限りは生かしておいほしい(経管栄養でもなんでも、延命措置をしてください)。
しかし近親者の顔も分からず、呼びかけに反応もできない状態になったら「チューブ」を「点滴」に換え、命の終わりを静かに迎えられるようにしてほしい。
と、このように書き残しても、事態が筋書き通りいくとは限らない。
ここから先は運否天賦(うんぷてんぷ)、人さま任せとなる。
(なんでもかんでも自分の意思通りにしたい、というのも人間の業(ごう)であろう)
意思能力あってこその「私の命」だ、その意思が失われたのなら否やはない。
何かの不都合でおかしなことになっても、もうわがままは言わないつもりだ。
《この記事の関連記事》▼▼▼
★《決定版!》最期の医療へ「私のお願い書」、軽々しく「延命拒否」とは書かない!!
<初出:2016年5月2日、最終更新:2022年12月2日>
■ □ ■
★PDF版『大事なこと、ノート』を作りました!
「延命は拒否する」と言うのは簡単ですが、命を投げ出す”予約”を健康な今のうちに自分で決めおくのがいいのでしょうか……。
老後は長いです。平穏に生きていることでさえ、実は容易ではない。
そんな自分が、いきなり死期や死後のあれこれについて注文つけるのは早計。
もっと考え尽くしてから、決めるべきかと思います。

一方、周囲の人が調べ直さなくて済むように、私の死後の煩雑な事務については、必要にして十分な個人情報を開示しておくべきでしょう。
なので、エンディングノートではなく、「大事なこと(を告げておくための)ノート」を作りました。
よろしければ、あなたに差し上げます。
考えるきっかけにしていただければ幸いです。
![]() 『大事なこと、ノート』PDF版は、下の囲みからお申し込みください。
『大事なこと、ノート』PDF版は、下の囲みからお申し込みください。
見出し又は画像をタップ/クリックすると、申込メールフォームにジャンプします。
※PDF版なので、必要ページを印刷してクリアファイルなどに保存してください。
気持ちが変わった時には、いつでも書き換え、追記できることが「利点」かと思います。
保険証・介護保険証・生命保険の証書・権利証なども一緒に保管しておけば、文字通りあなたの『大事なこと、ノート』になるでしょう。
『大事なこと、ノート』の詳しい解説はコチラ▼▼▼をご覧ください。
■ □ ■
《延命を考える》関連記事 =掲載日順
2016/1/12
★延命したいなら「鼻からチューブ」。父が脳梗塞、家族は突然に決断を迫られる!
2016/1/19
★父の「鼻からチューブ」で考えたこと。延命の可否、軽々には決められない!
2016/1/22
★父の病室にて 『人間なんて…』と思わないようにした………
2016/1/24
★よい病院、悪い病院──自分の命だ、患者も家族も真剣にならなければ守れない!
2016/5/5
★「延命のための延命は拒否」でいいですか⁉ 最期の医療めぐるおかしな“空気”
2016/6/3
★「寝たきり100歳社会」の悪夢、だって!?──人間はスゴイぜ!生き抜かなければ人生の価値は分からない
2016/6/5
★「延命のための延命は拒否」だって⁉ 命の問題に“空想”は無用だ!
2016/7/2
★延命処置、始めたら本当に止められない?! もっと”出口”の話をしませんか?
2016/7/27
★鼻チューブ・嚥下障害……やがて口から摂食。父は”今の自分”を生き切っている!
2016/9/16
病院よ、医者を見ずに患者をみてよ! 「診断書」遅延でわかった医療機関の体質
2017/1/3
▼▼▼父に鼻からチューブが施術されてから1年、私の気持ちは変わってきました
2017/6/22
★延命に対するあえて”私的なお願い書”!「尊厳死」などと猛々しくなく
2018/6/8
★延命拒否より“命を使い切る”選択!原点から180度変化した私
2018/6/26
★《決定版!》最期の医療へ「私のお願い書」、軽々しく「延命拒否」とは書かない!!
2019/4/10
★『大事なこと、ノート』第5刷でPDF版に!エンディングノート的要素を外し、百歳長寿時代を生きるためのノートに変えました
2022/12/7
★気軽に<延命拒否>だなんて言うな ! 今の医療は即実行。考え抜いて決断しないとヤバイ。『大事なことノート』活用下さい
2023/1/30
★『大事なこと、ノート』を刷新、PDF版に! 自身の後期医療を託す《医師へのお願書》付き
番 外
★『大事なこと、ノート』PDF版の申込メールフォームです(無料)
■ □ ■
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》
 家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)思い通りの相続を実現させるツールでもあります。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)
家族信託は全国対応a.jpg?ssl=1)
家族信託サイト.jpg?fit=708%2C154&ssl=1?1713475859)
『大事なこと、ノート』500.jpg?ssl=1)
『大事なこと、ノート』刷新.jpg?ssl=1)
断崖鼻からチューブ.jpg?resize=120%2C120&ssl=1)





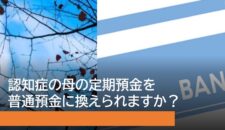



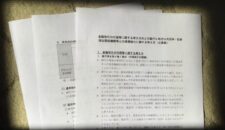
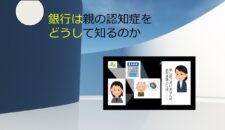




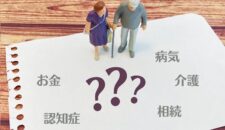


家族信託パンフレット.jpg?resize=312%2C217&ssl=1)

.jpg)